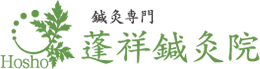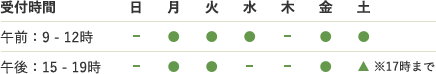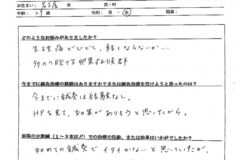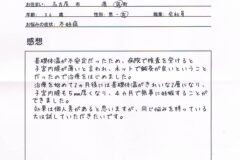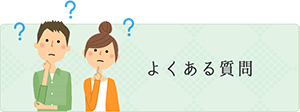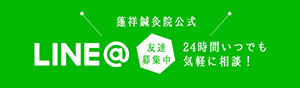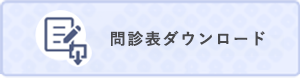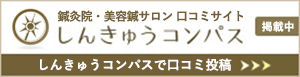不妊症や生理不順の原因となる多嚢胞性卵巣症候群の鍼灸治療 名古屋市中川区高畑の蓬祥鍼灸院
適応疾患
不妊症や生理不順の原因となる多嚢胞性卵巣症候群の鍼灸治療名古屋市中川区高畑の蓬祥鍼灸院
名古屋の蓬祥鍼灸院・長谷川です。
妊娠を希望しているため基礎体温を付けているが2層に分かれていない、生理周期が長い、排卵日が分かりにくいと悩んでいませんか?
このようなケースは多嚢胞性卵巣症候群の可能性が考えられます。
今回は不妊症や生理不順の原因となる多嚢胞性卵巣症候群どのような病気なのか、鍼灸治療の効果などについて解説していきます。
不妊症や生理不順の原因となる多嚢胞性卵巣症候群について

多嚢胞性卵巣症候群は不妊症の原因としても非常に多くみられます。
多嚢胞性卵巣症候群ってどんな病気?
卵巣にはたくさんの卵細胞があり、通常は1つの卵胞が成熟し、およそ2cm(20mm)くらいの大きさになると排卵します。
しかし、多嚢胞性卵巣症候群の場合は卵胞が卵巣の中にたくさんできてしまい、卵胞が成熟しきれないために未熟な卵胞がいくつもの卵胞が卵巣内にできてしまっている状態になります。
そのため、排卵障害が起きてしまうことで不妊の原因となってしまいます。
超音波検査では卵巣内にネックレスのような状態が診られるため、「ネックレスサイン」とも言われます。
多嚢胞性卵巣症候群の原因
多嚢胞の原因は現状ではしっかりと解明されておりませんが、以下のようなことが原因となっています。
- 脳の視床下部から分泌されるLH(黄体形成ホルモン)の分泌量の増加
- 血糖値を下げるインスリンの分泌量の増加
- 男性ホルモンの増加
- 肥満
- ストレス
一般的には肥満傾向の方がなりやすいとされています。
しかし、これは欧米人に当てはまるものであり日本人には比較的少なく、日本人の場合はどちらかというと痩せ型の女性に多く見られる傾向があります。
日本人の場合は若い頃は毎月生理が来ていたが、働き出してから不順になり、検査すると多嚢胞と診断される方も多いため、ストレスの関与が大きいのではないかと思います。
多嚢胞性卵巣症候群の症状
症状として一番の問題になるのが排卵障害による月経異常(生理不順)になります。
通常であれば排卵されるはずの卵胞がうまく育つことができないために、月経の遅れや無月経になります。
その他、男性ホルモンの増加による男性化や多毛、吹き出物などがあります。
多嚢胞性卵巣症候群の治療について
多嚢胞性卵巣症候群は不妊の原因になるため、できるだけ早期に発見し事前に治療をしておく方が良いと言えます。
妊娠希望ではない時期の多嚢胞性卵巣症候群の治療
まだ妊娠希望ではない時期に多嚢胞卵巣症候群であることがわかることもあります。
このケースでの治療の選択肢としては色々とあります。
- ホルモン療法
- 漢方薬
- 生活習慣の改善
中でも妊娠希望でない場合はホルモン療法を行うことが最も多いと言えます。
多嚢胞卵巣に対するホルモン療法
- 低用量ピル
- カウフマン療法
- ホルムストローム療法
いずれもホルモン剤によって人工的に月経周期を作り出すことでホルモン環境を改善させる方法になります。
漢方薬による治療
漢方薬に関してはホルモン療法と並行して行うこともできます。
もし、ホルモン剤の副作用がきついということになれば、漢方薬をメインに治療を行うことになります。
生活習慣の改善
肥満傾向の場合はまずは運動と食生活の改善により、適正な体重にする必要があります。
特に肥満傾向の方やインスリン抵抗があることがわかっている方は糖質制限もおすすめしております。
逆に痩せ型の方の場合もどうように運動と食事により良い意味で体重を増やす必要があります。
この時に重要なのがBMIという数値になります。
※例)62÷1.7÷1.7=21.4
この計算式で出てくる数字が25以上であれば肥満、18.5未満であれば痩せ型になります。
また、ストレスが原因となっている場合はストレス発散をすることやストレスを軽減させるために環境を変える必要も出てきます。
不妊治療としての多嚢胞性卵巣症候群の治療について
妊娠を希望される場合にはクロミフェン療法として排卵誘発剤であるクロミッドを服用したり、ゴナドトロピン療法としてHMG-HCG注射を使用して卵胞の発育・排卵を促進させていきます。
しかし、この注射を使用する際には卵巣が過剰に反応してしまう「卵巣過剰刺激症候群」や多児妊娠のリスクが出てきます。
また、重度の場合には手術によって卵巣に小さな穴を多数あけることでホルモンの状態を改善する治療法が行われることがあります。
多嚢胞性卵巣症候群の場合に自然妊娠できるのか?という疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、自然妊娠ができないわけではありません。
そのため、まずはタイミング法からスタートし、ステップアップしていくことになります。
多嚢胞性卵巣症候群に対する鍼灸治療

多嚢胞性卵巣症候群に対する鍼灸治療についてお話していきます。
多嚢胞性卵巣症候群に対する鍼灸治療の効果
まず1番気になるのが多嚢胞性卵巣症候群に鍼灸は有効かどうか?ということだと思います。
結論から言えば、多嚢胞性卵巣症候群にも鍼灸治療は効果があり、継続していくことで自然に排卵することが可能となります。
また、多嚢胞性卵巣症候群の治療となると病院で薬を使って排卵させる方法が一般的ではあります。
しかし、中には薬を使い過ぎたことによる副作用や薬の効きが悪くなる場合があります。
このような場合は一旦、薬の使用を中止し、鍼灸治療で身体の調子を整えるという方法もあります。
※当院では薬と併用しながら鍼灸治療を行う方が多くいらっしゃいます。
多嚢胞性卵巣症候群の原因はストレスによる気の滞りが最も多い
東洋医学の観点から多嚢胞性卵巣症候群の原因を探っていくと、最も多い原因がストレスによる気の滞りになります。
- 社会人になってから生理周期が乱れだした
- 結婚後の引っ越しによる環境の変化
こういったストレスが引き金となり生理周期が乱れることで婦人科を受診し診断されるというケースが多い印象があります。
もちろん、中には10代の頃から生理不順で婦人科を受診すると多嚢胞と診断されたというケースもあるため、必ずしもストレスが原因という訳ではありませんが。
しかし、多嚢胞とストレスはやはり非常に関係があるのではないかと思います。
そのため、ストレスによる気の滞りが原因となっている場合は気の流れを整えるための鍼灸治療を行っていきます。
鍼灸以外に多嚢胞性卵巣症候群の方が行うべきこと
鍼灸以外にも多嚢胞性卵巣症候群の方は以下のことも行っていきましょう。
- 運動
- 肥満体系であればダイエット
- BMIが18.5以下の痩せ型であれば体重を増やす
- 血糖値に問題があれば糖質制限
こういったことも多嚢胞による排卵障害を改善するためのセルフケアとしては大切になります。
多嚢胞性卵巣症候群に対する鍼灸治療の症例
【34歳女性】多嚢胞性卵巣症候群による不妊症
2019年に結婚するが、子供はすぐには考えておらず、1年半ほど前から排卵検査薬を使用してタイミング取るようになった。
その後、半年経過してもできなかったため、不妊専門の病院を受診すると多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)と診断される。
その他、卵管造影検査は問題なく、 夫側も特に問題なし。
病院での治療としてはクロミッド、またはセキソビットを交互に使用し、育ちが悪い場合はHCG注射を使用している。
半年前から人工授精をしているが、タイミングがなかなか合わないため2回してできていない。
鍼灸治療を希望される理由は多嚢胞性卵巣症候群の改善と共に、春〜梅雨の時期になると喘息症状が出てくるため、根本的に身体の状態を良くするため。
※喘息は症状がひどい時だけ麦門冬湯を服用している。
【その他の自覚症状】
息切れしやすい、食後の眠気、髪の毛が抜けやすい、胃もたれしやすい(元々弱く、朝食を食べると気持ち悪くなってしまう)、乗り物酔いしやすい、吹き出物ができやすい、緊張性頭痛、肩こり、物忘れ、のぼせやすい、下着を着替えるほどの寝汗。
- 脈診:右沈弦滑脈、左弦細脈
- 舌診: やや淡白舌、舌裏怒張マシ
- 気色診(顔色):心、肝胆、子宮膀胱白抜け、脾胃毛穴の開きあり、額に吹き出物あり
【弁証】:肝腎陰虚、脾気虚による多嚢胞性卵巣症候群、肺気虚による喘息
治療は週1回のペースで行っていくと、今までは上半身にだけ汗をかいていたのが、全身から汗が出るようになる。
また、手足の冷えも以前より気にならなくなる。
3診目の後にタイミングがあったため人工授精を行う。
4診目には喘息による息苦しさが出てきたため、喘息の治療を行うと、治療後には息苦しさは改善される。
5診目を終えた数日後に病院で検査を受け妊娠が確定するが、つわりも出てくる。
つわりが若干の凝っているが、喘息の症状も安定しているため7回で治療を終了。
多嚢胞性卵巣症候群の鍼灸治療まとめ
多嚢胞性卵巣症候群は不妊の原因としても珍しくない疾患となります。
病院での治療としては排卵誘発剤を使用していくことになりますが、人によっては効果が期待できないケースも珍しくはありません。
そのような場合は鍼灸治療も並行して行っていくことで基礎体温も徐々に安定していき、排卵することが可能となってきます。
選択肢は決して1つではないため、薬に頼りたくない方や薬によってダメージを受けた体を整えたい方は鍼灸もご検討いただければと思います。
この症状の患者様の声
関連記事

黄体機能不全の鍼灸治療
Contents 黄体機能不全について黄体機能不全とはどんな病気?黄体機能不全の場合の基礎体温の特徴黄体機能不全の原因黄体機能不全の検査と治療法検査方法婦人科で…

関節リウマチの鍼灸治療
Contents 関節リウマチについて関節リウマチってどんな病気?関節リウマチの主な症状関節リウマチの診断基準リウマチと診断されないこともあり関節リウマチに対す…

眼精疲労の鍼灸治療
眼精疲労が酷くて困っていたり、鍼灸って眼精疲労に効果があるのか知りたいと考えていませんか? 現代において眼精疲労はデスクワークによるPC作業以外にもスマホ、タブ…

PMS(月経前症候群)の鍼灸治療
生理前になるとイライラしたり、胸が張る、食欲が異常に増す、涙が勝手にでてしまう・・・という症状でお悩みではありませんか? このような症状が生理前にある方はPMS…

貧血の鍼灸治療
Contents 貧血について貧血とはどのような状態か貧血の症状貧血の種類と原因貧血の治療について鉄剤の服用食生活の改善原因疾患の治療貧血に対する鍼灸治療の効果…
ご予約・お問合わせ
当院は完全予約制です。
施術中、問診中は電話に出られない場合がございます。時間をおいてからおかけ直し頂くか、お問わせフォームまたはLINEにてお願いいたします。
名古屋市 蓬祥鍼灸院の
適応疾患
-
婦人科系疾患
不妊症・更年期障害・生理痛・生理不順・冷え性・子宮内膜症など
-
神経系疾患
うつ病・自律神経失調症・頭痛・めまい・不眠症・神経痛・神経麻痺など
-
皮膚科系疾患
アトピー性皮膚炎・ニキビ・円形脱毛症・湿疹など
-
運動器系疾患
関節炎・リウマチ・肩こり・五十肩・腰痛・坐骨神経痛・腱鞘炎・頸肩腕症候群・捻挫など
-
循環器系疾患
心臓神経症・動脈硬化症・高血圧・動悸・息切れなど
-
呼吸器系疾患
気管支炎・喘息・風邪など
-
消化器系疾患
食欲不振・胃痛・慢性胃炎・潰瘍性大腸炎・逆流性食道炎など
-
眼科系疾患
眼精疲労・緑内障・仮性近視・結膜炎・かすみ眼・飛蚊症など
-
代謝・内分泌系
疾患バセドウ病・糖尿病・痛風・貧血など
-
耳鼻咽喉科系
疾患中耳炎・耳鳴り・難聴・花粉症・アレルギー性鼻炎・メニエール病など
-
泌尿器・
生殖器系疾患膀胱炎・過活動膀胱・尿道炎・性機能障害・尿閉・腎炎・前立腺肥大症など